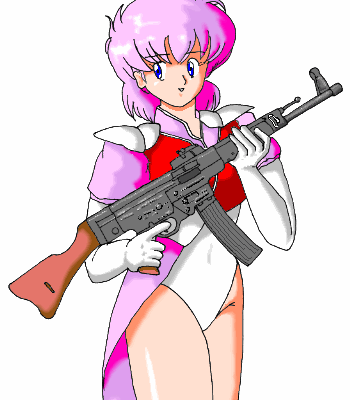 |
性能: 全長 940mm 銃身長 420mm 重量 5.21kg 使用弾薬 7.92mm×33 装弾数 30発 連射速度 500発/分 初速 650m/s 左図は自作です(^^;) 余談ながらストックはやや下にダレていますが、真っ直ぐの直銃床型もあったようですね。 |
||
現代の歩兵が遂行するライフルは「突撃ライフル」というジャンルのライフルである。この突撃ライフルというのは普通のライフルと違い、威力を落として対人専用とも言える(ようは装甲兵器には全く通用しない)弾を採用し、フルオート射撃も容易に行なえるようにしたライフルで戦後急速に発達したけども、その原点と言えるのがこのMP43だった。
7.92mm×57弾との比較試験の結果、400mでの距離の威力は決定的な差が出ず、威力も対人用としては文句はなかった。 さて、銃弾は完成し今度はライフルの番となった。ただ1939年にはドイツはポーランドに侵攻しイギリス・フランスがドイツに宣戦布告という世界大戦になったため、一時的にこのライフルの開発はストップした。ただ、MP40などの短機関銃の活躍が目覚しく、フルオートのできる突撃ライフルの活躍の場は十二分にあった。そのためか1938年に突撃ライフルの開発を開始していたワルサー社とヘーネル社での完成を急がせて1942年始めにはヘーネル社のMP43の原型であるMkb42(H)(Mkb=マシーネンカヤビニェール・・・機関騎兵銃)が完成し夏までには30丁が東部戦線に送り込まれ、実戦試験が行なわれた。結果は好評だった。ただ、1942年2月のホルム方面での記録写真にこの銃が写っているのがあるので、それ以前にも限定的に運用がなされていたのだろうか。余談ながら、ワルサー社でもMkb42(W)が作られて戦場での試験が行われていたものの、作動方式にローラーロッキング機構というものが備えられていて、当時にしては画期的だったものの、画期的すぎて正確な作動がえられず、ヘーネル社のガス式に敗れ去った。 戦場でも評判はよかったMkb42(H)は小規模な生産にうつされ、1942年11月から1943年4月にかけて8000丁もの生産が行なわれた。これ以降は改良が行なわれ、MP43として生産が行なわれる事となる。ここからMP43の歴史が始まるのだが、その生い立ちは平坦なものではなかった。1943年7月には東部戦線のクルスク戦での敗北もあり、主導権が完全にソビエト軍の手に落ちたこともあり、このライフルの大量生産・大量配備は悲願でもあったのだが、ヒトラーはこのライフルの生産を禁止した。理由は補給系統が混乱するからだった。同じ部隊で違う弾薬を用いるライフルを使えば補給部隊が困る。これは日本の例を見れば分かる。たしかにわかるのだが、前線からは突撃ライフルの配備要請が相次いだ。困った兵器局はバレないようにあたかも短機関銃を生産しているように見せかけて「MP43」と名づけて細々と生産を行なって戦場に送っていた。書類上では「短機関銃」なのでヒトラーの目もごまかせた。1943年中に14000丁ほどが生産され戦場へと送られた。この数字は300万人のドイツ軍が展開している東部戦線での需要を満たす分にはほど遠い生産数でしなかなく、実際の所は大量生産を兵器局も前線部隊も望んでいたのだった。 補給面以外にも、MP43の大量生産・配備を阻害していた理由の1つに、ドイツ軍の歩兵分隊(10名ほどの1単位)に1丁ずつMG34かMG42が配備されていた点もある。両機関銃はベルト給弾式で発射速度および性能も素晴らしく、特に分隊に1丁ものベルト給弾式機関銃を配備していた国はドイツ以外にはなかった。そのため、当時のドイツ兵の教本にも分隊の兵士は機関銃の護衛や弾薬運びのお世話係にしかすぎないと謳われていた。分隊単位でならドイツ軍ほど火力が優れていた部隊は他国にはなかった。 ただ、イザ戦闘になるといろいろと問題は直面してきた。歩兵戦は海戦や空戦と違って最終的な戦闘単位は兵士1人になる。特に機関銃の発達で散兵戦術が主流になると2人1組での行動も多くなった。そうなると機関銃は支援用で使わざるを得なくなるのだから、最終的には兵士個人の火力を増やすしかなかった。ロシア北方戦域の森林地帯ではボルトアクションのKar98kがあまり役に立たず、兵士全員に短機関銃のMP40を持たせた部隊もあったと言われている。 「機関銃は重要な頼れる戦力」に違いがないのは今も昔も同じだが「機関銃が主役」という考えは他国では浸透しなかった理由はここにあるだろう。でなければ今でも歩兵のライフルはボルトアクションライフルかセミオートライフルだろうから。 1943年12月。東部戦線で功績のあった将軍3人をヒトラーは招聘し叙勲を行い功を労(ねぎら)った。ヒトラーは将軍3人に対して「何か望むものはないか?」と質問し3人全てが「MP43」と答えた。MP43というのが自分が生産を禁止していた突撃ライフルであった事を知ったヒトラーは怒りを隠せなかったが、功績のある将軍の頼みでは即座に「イヤ」とは言えない。ヒトラーは実態調査を命じ、その報告を待った。帰ってきた報告書には部隊の配備要請の多さだった。ここにきてヒトラーは自分の考えを改めて生産を正式に許可したのだった。ただし名称はMP44と兵器分類上はあくまでも短機関銃だった。1944年12月からはStg44(Stg=スチュームゲベール・・・突撃ライフル)と改名した。改名した理由は、この時期にエルマ社から44型短機関銃(MP44)という短機関銃が採用されたことが第一の理由だろうが(おんなじ名前だと当然ながら紛らわしい)、戦意高揚的な意味合いがあったと思われる。ちなみに、エルマ社のMP44短機関銃は後に「EMP44」として名前が通る事になり、普通「MP44」といえば本銃を指すようになった。哀れ、エルマ社のMP44(;_;)。 やっとにして大量生産が実行できたのであるが、時すでに遅かった。もはや突撃ライフルの生産ピッチよりも連合軍の進撃速度の方が各段に速かった。オデッサ・ノルマンディ・カレリア・ファレーズ・クールランド・ワルシャワ・アルデンヌ・レマーゲン・ブダペルト・・・ドイツの先はもう見えていたのだった・・・。 MP43・MP44・Stg44を合わせた生産数は525000丁と言われている。この数字だけでもドイツ軍が欲した数に遠く及ばなかったのに、実際には輸送網が連合軍の爆撃で破壊されて破綻寸前にあったせいもあり戦場にとどいたのは生産数の3分の1以下でしかなかった。残念ながらドイツ軍が欲した10分の1の数しか戦場にとどかなったというわけである。 ただ、その遺産はソビエト軍に引き継がれ、名突撃ライフル「AK47」を生む原型ともなったといわれる。たしかにソビエト軍は突撃ライフルというジャンルの銃を高く評価しており、戦後に即突撃ライフルを作り上げた柔軟さは多いに評価していいだろう。すぐに作れた理由に銃弾自体がすでに完成していた理由もあった。ただ、そのままのコピーではなく、グリップと銃床間を短くしたり、弾倉も少し短くしてから銃床を少し下げて伏せ撃ちも可能にして、弾倉交換方法もスイング式を採用して伏せた状態でも弾倉交換をできるようにした。またハンドガードも木製にして射撃の過熱で保持できないのを防いだ。ここにきて突撃ライフルは完成を見たと言ってもいいかもしれない。 しかしながら、アメリカでの評価は悪かった。捕獲銃のテストレポートでも簡単な記載しかなく、それも「威力がなく(我が軍の)M2カービンにも劣る」といったものしかなかった。これを「MP43は大半が東部戦線に送られたから西部戦線ではあまり使われなかった」からとしている文献も多い。ただ、1944年末のイギリスにあるアメリカ陸軍基地の捕獲銃展示写真(自軍兵士に敵はどういう銃を使っているかを教えるための展示)にはすでにMP43は写っているため、西部戦線でも組織的に使われていたのは間違いない。ただ、そのキャプションにはなぜか「MP40」と誤って表記されており、説明文にも「MP38よりも発射速度は遅く、重量は若干重い」としかない。アメリカ側では威力が少しある短機関銃としか見なしていなかったのだろう。 殆ど全ての文献で、「MP43は新ジャンルの歩兵用ライフルである。それを見ぬけなかったアメリカ側西側の銃器は大きな遠回りをした」と書かれている。間違ってはいないとは思う。ただ、私見ながら、アメリカ側の考えが間違っているとは言い難い一面もあるのではないか?。実際に手にとって操作してみると分かるが、伏せうちなどまずできないぐらいに長い弾倉、MP40と同じ操作を要求されるコッキングハンドル(MP40では右手でグリップを握りながら操作できるように、左側面にコッキングハンドルがあった。MP43でも同じく左にある)など、どう考えても、「ライフルの延長線上」ではなく「短機関銃の延長線上」として設計したんじゃないかと思えなくはない。結局アメリカは弾薬の短縮化はせず、小口径化という新ジャンルのライフルを採用して、それが世界スタンダートになっていった。小口径化の始まりはアメリカである。その点を考えても「アメリカは新ジャンルを見ぬけなかった」と安直に評価するのはいかがなものかと思える。 ただ、別にMP43をけなしているつもりはない。むしろ褒め称えたい。既存の考えにとらわれず設計し、また戦時生産に対応した生産方法を確立もさせた。そんなどんな銃ともわからぬものを採用したし、ヒトラーから生産を禁止されてもなお生産を続行したドイツ国防軍も含めて大きく評価してよいだろう。 MP43は生産途中でMP44とかStg44と名称を変更しているけども、実質的には同一の銃器だった。ただ、当時の写真を見るとストック部分がいくつかの改良が行われていたらしい。MP43のすばらしい所は生産性の良さもあった。銃床は木だけども、金属部分はプレス加工を多用してわずか14時間で作れたというから分業をおこなえば大量生産が容易だった。ソビエト初の突撃ライフルAK47の機関部が削りだしでやや時間がかかった点を考えればMP43は出現時点で完成されていた突撃ライフルと言ってもいい。 分業が可能なため、部品だけ別の工場で作らせてそれをかき集めて組みたてるという方法も確立された。これは当時としては驚異的な生産方法だったと言える。特にドイツの工業水準は高いため精度の良い部品が作られたから日本みたいに組みたてたら不良品しかできなかったという事態にはあまりなかなかった。この方法には欠点もあって、どこかの工場の部品がロット単位の不良をおこした場合、1つの組みたて工場に部品が集まるせいもあって、その特定が難しかった。特に戦時中は行程簡略化のためと組みたてた銃が敵に鹵獲されて製造工場を特定されてそこが爆撃されないようにあまり刻印を打たなかったために余計にその特定は困難を極めた。また、一番の欠点はドイツの輸送網が爆撃を受けて混乱状態にあったのと、他の物資輸送で精一杯だったために、なかなか集めるのに苦労をした点もある。同様の理由で戦場に送るのもままならなかった。 MP43の操作性だが、これはかなりいい。安全装置はグリップ左側面の前方にあり、またこのレバー自体が長いので持ちかえずに操作ができる。下げるとセフティで挙げると解除になる。個人的に言わせてもらえれば、逆な方が即座に撃てていいような気もする。 MP43のはセミオート(単発)とフルオート(連発)で撃てるためセレクターもあるが、これはレバー式ではない。グリップ上の方にボタンがあり、これを左側面(安全装置がある方)から押し込めばフルオートになり、逆から押し込めはセミオートになる。即座にフルオートにできるのは大きな強みだろう。ただ、MP43を受領した部隊やMP43で訓練した兵士には「フルオート射撃は緊急時・絶対に必要な時以外には使用するな!」と厳命されていた。不必要な弾薬の浪費を防ぐためだが、フルオート機能があるとどうしても使っちゃうのが人間の弱い所だし、MP43が本格的に配備されるようになると、戦局はもはや悪くなりつつある一方だったので戦闘になればいつもが「絶対に必要な時」となったことだろう。 弾薬はライフル弾と同じく5発クリップに入って支給されていた。そのため短機関銃とちがって、弾薬の装填は結構容易に行なえた。ただ、現存する当時の弾薬を見る限り20発入りの箱に入って部隊に支給されていたようで、30発入りのMP43の弾倉に対して中途半端ではなかろうかと思えなくはない。 あと殆ど論じられない利点として、射撃音がある。実弾射撃をやった事がある人ならわかると思うが、銃の射撃はとってもやかましい。特に威力がある銃弾ほどやかましくなってくる。拳銃弾でも90dbは容易に突破するしライフル弾ともなれば110dbはゆうに超える。MP43の射撃音量はライフル弾に比べれば小さい。それでも100db弱と推定されるがなんとか耳栓なしで耐えられる音量ではある。それが兵士に好評であった一因とも言えなくはない。 ただし、欠点もあるにはあった。 まず、ハンドガードが金属なので加熱されやすかった。銃器は5発も撃てば結構加熱される。そのため1マグ30発も撃てばハンドガードが持てないぐらいに加熱されてしまった。人間は50℃でも保持ができなくなる。そのため実戦では弾倉を持って射撃をしていた。持ってみるとわかるが、ストックからハンドガードまでが結構長く、実際に保持すると、マガジンハウジングを持った方が安定する。 この弾倉も7.92mmという大きい口径の弾を30発も積め込んでいたのでやたらと長く、伏せ撃ちが難しかった。無理だったといってもいい。地べたに穴を掘ればすむが、いちいちそんな事はしなかったろう。 照準の照門が剥き出しでしかも、銃本体よりもかなり高い位置にあるので、ここが落としたときなどに破損しやすい点も指摘されている。 あとは重たい(30発弾を込めた状態だと6キロ以上ある)点も欠点いえばそうだろうが、反動を銃の重量でかなり吸収するので欠点とも言えないかもしれない。しかしこれを持ってテクテク歩く歩兵にとっては大きな欠点と思える。 それと実際にMP43を持ってみればわかるが、トリガーハウジンググループ(機関部の下半分)がグリップを含めて1枚板からプレス加工して作られているので、グリップを持ってみると四角い箱を持っているような印象を受け、お世辞でないと「持ちやすい」とは言えない。 コッキングハンドルがなぜか銃の左についているので、はっきりいって操作しにくい。伏せうちでの操作は全くといっていいほど考えてなかったと思える。 バリエーションとして、クルツ(短)弾薬の利点を生かして、クルムラウフ(曲射銃身)型も作られた。30度曲がった型は照準にプリズムをがいして照準するもので、射手自体は完全に物陰に隠れての射撃が可能だった。ただし実戦ではあまり役に立たなかったといわれる。極端なものは90°曲がった銃身も作られた。これは戦車兵用で砲塔に隠れてから射撃できるようにしたもので、照準器はなく、目視での着弾点を見てから狙うものとした。その気持ちはわからんでもないが実際のところは使えたのだろうか?これを捕獲した連合軍が試験する記録写真があるが、実戦で使われたかは不明。 銃自体のバリエーションではないが、このMP43に赤外線照射装置と受信機をつけた型もごく少数ながら生産された。この装置自体、銃がひん曲がりそうになるぐらいに重く射手も相当な体力が必要だったろう。あと、赤外線照射装置は相手が同じ受信機を持っている場合、照射と同時に撃たれる危険性もあった。この装置はドイツとアメリカのみが実用化しているので、この装置を持たないソビエト軍相手の東部戦線ではそこそこ使えたと考えられる。 |
|||
