発射
↓
発射の反作用でスライドが後退開始
↓
でもバレルとスライドがかみ合っていて固定されている
↓
ある一定の距離を進めばバレルが少し下に動いて噛み合いがなくなる
(その間にすでに弾は発射されている)
↓
スライドとバレルが開放されてスライドはその慣性で後退する
(弾が発射されているのでガス圧は相当低くなっている)
↓
スライドは引ききって空薬莢を排出してスプリングの力で前進してその時に
次弾を装填する。
↓
飛んでいった弾はあたかも固定されたバレルで撃ったも同じなので命中精度がいい
↓
(゚д゚)ウマー
です(謎)
これだけでは分からないと思いますので(当然だ(^_^;))図解で示したいと思います。
まず、目標を定める!
Lesson1
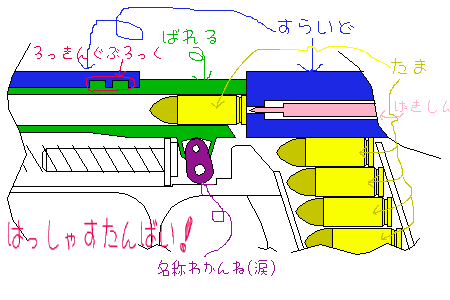 |
右図がショートリコイル式拳銃(U.S.M1911A1拳銃"ガバメント"をモデルにしています)の模式図です。かなりハショってますが勘弁してください(;_;) ちなみに左図の「名称わかんね(涙)」という所の部品は「バレルリンク」だそうです。ひらだいら へいぺいさん、くりんこふさん、教えていただきありがとうございます 発射スタンバイOK状態を表しています。この状態で引き金を引けば弾が発射されます。 赤丸部分がロッキングブロックでここでバレル(緑色のやつ)とスライド(青色のやつ)がガッチリガードしています。 発射させると、撃針が銃弾の雷管を叩いて火薬を急激に燃焼させ(ようは爆発)銃弾を発射させる。この際に作用反作用の法則で(物体を動かすとその正反対に同じだけの力がかかる)銃自体が後ろに下がろうとします。大抵は人間の手で固定されているのでスライドが下がろうとします。スライドを固定すればいいけども、それでは自動拳銃の意味がない。反動を利用して排莢と弾薬の装填をするのだから。 ただ、そのままだと発射ガス(数千気圧にもなる)で強烈にスライドが後退するので(最悪、スライド脱落の恐れがある)銃弾発射後に発射ガスがある程度銃口から出させて気圧をある程度下げてから反動慣性でスライドを後退させる。 |
Lesson2
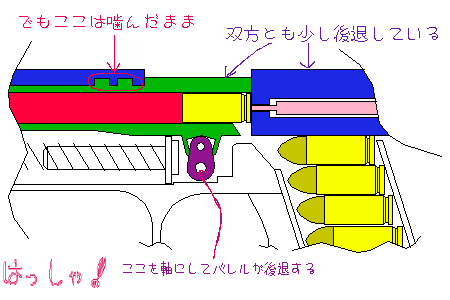 |
発射! 発射すると同時に作用反作用の法則で銃に固定されていないスライドが後退を開始する。ただし、ロッキングブロックがガッチリ噛んでいるのでバレルとスライドは固定されていてバレルといっしょに少し下がる。左の絵からもうちょい下がるとロッキングブロックが開放されてしまう。ようはバレルとスライドを固定している時間はほんの一瞬なんだけどもそれでも充分。銃弾がバレル内を動く時間はほんの0.001秒なのだから。その一瞬の間でも、バレルの固定・発射気圧を下げる時間としては充分すぎる。 |
Lesson3
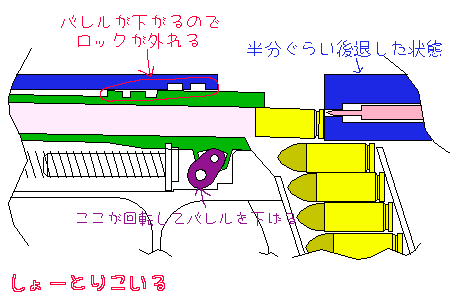 |
ロッキングが開放された状態。 開放された時点ですでに発射気圧はある程度下がっている。ただ、慣性は働いているのでその慣性でスライドはめいっぱい後退する。バレルもティルト(傾く)する。ティルトすると左絵みたいに銃弾ガイドとくっついて次弾装填がスムーズにいく。 左の絵から先はもうちょいスライドが下がると空薬莢が排出され、次弾が少し上に出て、バネの力で元の位置に戻る際にその次弾を押し上げて薬室にもっていって次弾の発射スタンバイはOKとなります。そいでLesson1からまた繰り返しとなります。 このように、バレルが少し(ショート)後退(リコイル)するために「ショートリコイル」という名称がつけられました。特許はブローニング氏の所属するコルト社が持っていましたけども(当然、今は特許切れだけど)、その時の申請名がこれだったのかしら? |
|
というわけで (゚д゚)ウマー
です(謎) ちなみに、上記はブローニングタイプショートリコイルで今では多くの拳銃に見受けられます。ロッキングブロックが別部品になっているものもありますし(ワルサーP38など)ルガーP08のようにトグル式のもあります。ただ、別部品になるとコストがかさむ事と構造を単純にできる関係で今ではこのブローニング式が一般的です 昔は機関銃もこのショートリコイルタイプでした。特に戦車用車載機関銃の場合、別項で述べるガス圧式だと車内に一酸化炭素満載の発射ガスが充満して戦車兵が気絶してしまう可能性があるのでこのショートリコイル式は都合がよかった点もあります。ただ、拳銃と違って機関銃はバレルが長くその分重いので、その重いバレルを前後させるのはあまり効率的とはいえず、今ではガス圧式が主流となっています。 |
戻る