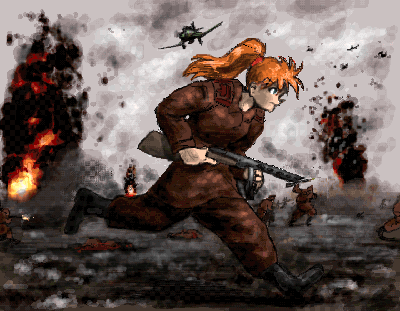|
性能: 全長 836mm 銃身長 272mm 重量 4.75kg 使用弾薬 7.62mm×25 装弾数 ドラム71発 装弾数 箱型 35発 連射速度 900発/分 左は自作です 下の絵はAnpontanさんからいただきました。 資料の一部は紅葉饅頭さんから情報提供をしてもらいました。ほんとにありがとうございます ≦(_ _)≧ |
||||
| PPSh1941とは、「Pistolet Pulemjot Schpagina model of 1941」の略でそのまま訳せば”シュパーギン機関拳銃1941モデル”ということになるだろう。また、一般にはPPSh-41と西暦の最初の2文字(ようは19)を略して紹介されることが多い。ここではPPSh1941という名称で統一したい。 短機関銃というジャンルの銃器が登場したのは第一次大戦からだった。当初の目的は航空機搭載機関銃用だったと言われている。「飛行機に拳銃弾当てても意味ねぇじゃん」と思う人が多いかもしれないが、第一次大戦の頃の航空機は布張りで防御力などないに等しかった。実際、初期の空中戦は拳銃の撃ち合いが行われていた。しかし、普通の機関銃の搭載がなされたため、短機関銃の航空機機銃という意義はなくなった。そりゃエンジンさえ撃ちぬく普通の機関銃のほうがいいに決まってる。 さて、陸上兵器としても短機関銃は注目された。第一次大戦は塹壕戦でその突破が第一の目的だった。射程なんて短くていい。敵に肉薄して弾をばら撒き敵に自身の血の雨を降らせたい!。そういう意味合いでドイツで使われた。1918年のドイツ最後の攻勢時に使われたというが、結果はいまいちだったという。 大戦間に、短機関銃は発展を遂げた。クローズアップされるのはアメリカにおけるギャングの使用だった。当時はフルオートできる銃器販売にやかましくなかったのか、マフィアが大量に装備していて、対立抗争時に多数が使用された。取り締まる警察側も対抗上短機関銃を装備するようになった。使われた理由は、ギャング同士の抗争で野外戦闘など起こるはずもなく大抵は街の中だった。距離は遠くても50ヤード程度だったろうから拳銃弾でも問題なかった。相手を威嚇する面でも存在意義は大きかったろう。 「短機関銃=ギャングの銃」 という考えが一般人にも浸透しているのは「アンタッチャブル」などの映画の影響が多大といえるが、そういう理由なのだろう。
また、第二次大戦では別の観点で短機関銃の需要があった。ドイツ西方電撃戦(1940年の攻勢)で大量の装備を失ったイギリスは手間のかかるライフルではなく、簡単・安価に製造できるステンガンという短機関銃を大量に生産・配備した実績があった。同じドイツを敵としたソビエトも例外ではなかった。 話はさかのぼって、ソビエトが短機関銃を開発したのは1926年だと言われている。ただ、文献のみで伝わるもので、その写真も図面もないし、ほとんどの資料では触れられていないので、本当に存在したかは疑問が残る。確実に開発開始がなされたのは1934年の事で、V・A・デグチャレフが開発を開始した。当時は戦争をしているわけでもなかったので、開発はのんびりと行われ、完成したのが1938年だった。PPD1934/38と命名されたこの短機関銃は翌年の1939年にソビエト軍によって採用された。初陣は同年11月30日から始まった対フィンランド戦、いわゆる冬戦争からだった。ただ、主だった活躍はあまり聞かない。この戦争でフィンランド軍が使用していたスオミ短機関銃が使っていたドラム弾倉に目をつけたソビエト軍は早速PPD1934/38用のドラム弾倉を製作した。ただ、PPD1934/38は元々が箱式弾倉でこれをそのままドラム弾倉につかうのにはマガジンキャッチに負担が大きすぎた。そのためマガジンキャッチを改良したPPD1940が作られた。 PPD1940は優れた短機関銃ではあったが、ソビエト軍はさらにこの短機関銃を改良するように求めた。とにかく生産性を最優先しろというものだった。1940年といえば世界に目を向ければ、ドイツがフランスに侵攻し制圧した時期で、またソビエトも冬戦争でフィンランド戦に辛うじて勝利を収め、一応戦争はしていなかった頃で、なぜそんな時期に主力兵器でもない短機関銃の改良を命じたのかはよくわからない。フィンランドのスオミ短機関銃によほど刺激されたのか。もしかしたらこの頃からドイツとの戦いを意識していたのかもしれない。 それに応えたのがゲオルク・シュパーギンという設計者で、プレス加工を多用し、多少の精度誤差がでようとも、組立が可能なようにした。また部品点数も極力減らすなどの設計を行った短機関銃を完成させた。それがPPSh1941だった。この狙いは別の意味で大成功を収めた。
ただ、大量の将兵と武器を失ったには違いがなく、ソビエト軍はその装備と兵員を補充する必要があった。ソビエトにとって幸運だったのは人口が多い事で、人員はなんとか埋められた。ただ、工場地帯がドイツ軍に制圧され、ウラル山脈付近に疎開していたこともあり、ライフルの生産は遅々として進まなかった。徒手(素手)の兵隊が何の役にたとうか。とにかく簡単な銃を作って持たせようと、簡単な構造のPPSh1941に白羽の矢がたった。 「バレル(銃身)が足りない?じゃあライフルのバレルを半分にちょん切って使え。2丁分確保できるぞ」 そんなこともやってたらしい。連発で撃てるため特別の訓練もいらず、とにかく、数を揃えて戦場に送りたかったソビエト軍は(実際に戦闘訓練などさせずに戦場に送り込んでいたらしい)とにかくPPSh1941を大量に作りまくった。 ドイツ軍での短機関銃の装備率は11%ほどだったという。たしかに1個分隊11人で分隊長1人が短機関銃を持つのだからだいたいその程度だけど、ソビエト軍の場合は34%にも及んでいたという。その大量生産・大量配備のほどが知れるではないか。 PPSh1941の配備は終戦までおよび、そして使用された。戦争中により簡略化されたPPS42やPPS43が採用されていったものの、完全に取って代わることはなかった。500万丁とも700万丁とも言われる数が生産されたPPSh1941だったから、いまさらとってかえることなど経済的負担の何物でもなかったろうし、これらの短機関銃と比べても別に性能が悪いと言う事もなかった。また、これが一番の要因だろうが、別に兵士はPPSh1941を嫌っていなかったからだろう。 71発という大量の装弾数は実戦的で、ドイツ軍兵士も、このPPSh1941を好んで使用したという。ただ、逆にソビエト軍兵士はドイツ軍のMP40を好んだといわれる。隣の芝生は青くみえるものなのだろうか? 当然ながら、対日戦にも登場し、特に占守(しゅむしゅ)島攻防戦でも大量に使われた。占守島攻防戦では接近戦が多く、日本兵の手記にも、このPPSh1941を褒めている表記も見受けられる。 それ以降はAKという傑作突撃ライフルが登場したため、PPSh1941の存在価値がなくなり、やがて、制式配備から消えていくこととなった。ただ、空のIl-2シュトゥルモビク・戦車のT-34・銃器のPPSh1941・そしてソビエト人民の愛国心とソビエト連邦を救った大きな原動力の1つだったのは間違いない事実だろう。 PPSh1941は俗にその文字をとって「ペーペーシャー」と呼ばれていた。ちなみに、ドイツ兵は「バラライカ」と呼んでいた。語源はよくわからないが、たぶん楽器の名前だろう。ちなみに、日本兵は「マンドリン銃」と呼んでいた。日本兵の手記に散見される。 PPSh1941の特徴といえば、単純構造でオープンボルトブローバック式の短機関銃だった。外見的にはオーソドックスな形状だけども、単発・連発のセレクターは引き金の前方にあったし、排莢口は上についていた。スリングスイベルが銃左側面にある点を除けばほぼ左右対象構造だった。左利きの射手でも問題無く撃てたのも大量の兵士が使用する銃器ということを考えれば大きな利点だったといえるだろう。排莢口が真上にあるので、射撃時の照準がしにくいのではないかとも思えるが、命中率云々というジャンルの銃でもないので問題はなかったと思える。 他の利点といえば、ドラム弾倉使用で71発という驚異的な装弾数を誇っていた点にある。特に戦場ではすごく焦るために弾倉交換(マガジンチェンジ)が思うように出来ない場合があり、そういう面でも71発収められたこのドラム弾倉の意義は大きかった。あとは銃本体の生産性の良さもあるだろう。銃床(ストック)と機関部下面が木なのでそのへんは加工が大変だったろうが、ソビエト製の銃器は日本製と違って仕上げが粗く、結構手を抜いていたのではないかと思えなくはない。ただ、頑丈な作りな上に生産性の良さを上げるために部品点数も極力少なくしており、また、多少の部品寸法誤差があっても確実に作動するようにクリアランスも若干大きめに設計されていたために、砂塵が入りこんでも確実に作動したと言われる。その理由で命中精度はあまりいいとは言えないが、上でも書いているが、命中精度のどうこういうジャンルの銃でもないので問題はなかったろう。多少の汚れに強いというのは戦場においては大きな利点となったはずで、ドイツ兵が好んで使った理由もこのへんにあるのだろうか。 ただ、欠点もあるにはあった。その形状上保持が難しかった。特に左手の保持部分が握り場所がなかった。ドラム弾倉は持ちにくかったので弾倉と引き金の間部分を持っていたか、あるいはオープンサイトの照準射撃は諦めて腰だめで撃っていたのだろうか? ドラム弾倉自体も欠点の1つといえた。71発入るのは大きな利点だが、弾込めもその分時間がかかった。71発ドラム弾倉の装填手順は、まずは弾倉前方のゼンマイをまいてバネを圧縮させてそのストッパーをかけてからから弾倉口のフタをあけて1発1発込めていたが、普通に考えても大変な作業というのは分かるだろう。71発込め終わったらちゃんとバネのストッパーを解除して、ちゃんと並んで装填されているかを確認するために、2発程度指で弾をはじいて確認する必要があった。無論、上手く上がらないならば場合によってはもう1度やり直す必要があった。それならいいが、装填途中でストッパーが外れるというまでもなく弾がボロボロとこぼれた。なだけならいいが指を怪我する可能性も大きかった。しかも、ドラム弾倉は生産に手間がかかるために、後には35発箱型弾倉が作られて配備された。たしかに第二次大戦末期のソビエト軍兵士の手に持っているPPSh1941には箱型弾倉がついているのが多い。 |
|||||
戻る