 |
全長: 4.85m 車体長: 4.85m 全幅: 2.40m 全高: 1.89m 重量: 11.8t 装甲: 8〜18mm 乗員数: 4名 搭乗歩兵: 6名 左写真はいちのへさんから提供していただきました。 どもありがとさんです ≦(_ _)≧ あと左写真は試作型で本チャンの型とは形状が若干ことなります(^^;) |
武装:12.7mm機関銃×1 (840発搭載) 7.62mm機関銃×1 (1500発搭載) 動力:三菱8HA2 220馬力ディーゼル 4サイクル水冷 8気筒V型 走行性能:最大速度:45km/h 総生産台数:??? |
|
昭和30年代になってくると、日本の経済も安定してきた。現実的な脅威としてソビエト軍がいた。結果的に攻めてくる事はなかったものの、その強大な軍事力は脅威だった。それまではアメリカ軍装備に頼っていたものの、日本でも補給などの関係や、やはり1国の独立国家としては自国の護りは自国の装備でという意地もあったのだろう。昭和35年頃になると日本が自主開発した兵器が制式化されるようになってきた。61式戦車や60式自走無反動砲、64式小銃などである。この60式装甲車もその1つだった。 開発経緯は戦車に追従できる機動力を歩兵に与えるためだと思うけども、乗車人数が6人と中途半端である。2両1組として考えられていたのだろうか?ともあれ、陸上自衛隊の主力装甲車として使われていた。しかし浮航性がなく、NBC(=核兵器・毒ガス兵器・細菌兵器)保護の点でも欠如していた。そのため昭和42年からは新しい装甲車が開発され昭和48年に73式装甲車が仮制式されるものの、73式装甲車の値段が高く、完全にそろえる事はできなかった。そのため73式装甲車制式後もずっと使用されつづけて今に至っている。 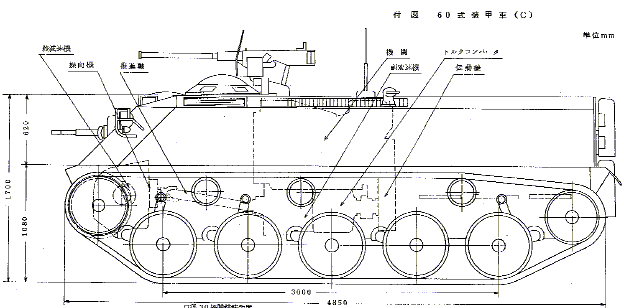 車体外見的にはアメリカのM113装甲車をそのまま車体高を低くしたような印象を受ける。実際、車体高以外は寸法はだいたい同じで重量もほぼ同じ。ただし、居住区がそれに比例して狭いので、M113は11人乗車に対して60式装甲車は6人しか乗れない。また派生型もM113はいろいろあるけども、60式装甲車は小さいので、派生型といえば60式自走迫撃砲などしかない。小さい事は弾に当たりにくいという利点があるものの、小さいからそれが利点だとは言いきれない面もあると言える。乗員は4名で内訳は車長・操縦手・7.62mm機銃手・12.7mm機銃手となっている。後ろの兵員室に6名が乗車できる。なお予備で1席設けられている。ただし、ガンラックは予備座席分はない(6丁分しかガンラックがない)。些細な事だが、ガンラックはM1ガーランドライフル用になっている。制定当時は64式小銃が存在せず、自衛隊の制式ライフルはM1ガーランドライフルだったからだけども、防衛庁通達で60式装甲車の改訂が何度か行われているけども、ガンラックがつねにM1ライフル用になっている。確認が出来る限りでは60式装甲車に関する最後の通達は昭和62年11月7日に出されているけども、これでも「小銃銃架:M1ライフル用」とある。融通のきかない日本の役所を感じさせる。 使用用途は敵銃砲撃下でもつとめて突入できるようにというコンセプトで、あとは、指揮・通信・補給(物資の輸送)・患者護送などに使うようになっている。また牽引装置で2トントレーラー(弾薬などを搬送する)も牽引できるようになっている。 武装はブローニングM2重機関銃(12.7mm機関銃)1丁とブローニングM1919A4機関銃(7.62mm機関銃)1丁が装備されている。弾薬は12.7mm機関銃が105発入り弾薬箱8個の都合840発で7.62mm機関銃が250入り弾薬箱6個の都合1500発が搭載されている。12.7mm機関銃弾は戦車では500発弱が標準だけども、この60式装甲車では結構多く積んである。360°全周射撃が可能だからよく使うだろうと判断されたのだろうか? エンジンは220馬力だけども、これは改良された形跡がない。同年同月同日に採用された60式自走無反動砲はエンジンの改良がなされている。たとえば排気量を半分以下にしたにも関らずエンジン出力を120馬力から150馬力にパワーアップさせているが、60式装甲車は排気量が10800ccのままで馬力の220馬力のまま。73式装甲車やら89式歩兵戦闘車が登場したからそういった改良がおざなりになるのは仕方がない事なのだろうか? |
||
一覧に戻る