|
全長: 9.60m 車体長: 9.60m 全幅: 3.43m 全高: 3.20m 重量: 45.0t 装甲: 最大25mm 乗員数: 11名 |
武装:16.5口径76.2mm砲×1 46口径45mm砲×2 7.62mm機関銃×5 動力:イスパノイザM17M V型12気筒 500馬力ガソリン 走行性能:最大速度:29km/h 航続距離:151km 総生産台数:61両 |
|
|
第一次大戦から第二次大戦の間の大戦間はいろいろな戦車がデビューした。今の眼でみれば、「何を考えているのか・・・」と思われる戦車もいくつかあった。ただ、この時期は戦車の用法は手探りの部分が多く、一概に一笑できない所もたしかにあった。用法が変われば戦車も変わる。これはいたしがたない点ではあった。 第一次大戦の戦車は例外なく遅かった。装甲も薄かったので砲撃で簡単に撃破できた。そのため、戦後は速度重視で作られるようになったものの、一方で遅くても重武装で敵防衛陣地(塹壕など)を突破しうる戦車もいくつか作られた。当時はエンジン馬力の関係で、重武装と高速度が両立できなかった以上これはやむをえなかったといえるだろう。実際、重戦車と快速戦車が統一されるのは第二次大戦後しばらくしてだった。重戦車といえば、重装甲で鈍足なイメージがあるが、初期のそれは多少意味合いが異なっていた。塹壕を突破するために、車体がかなり長く、多くの敵と対峙するために、武装を多くする。これが求められた。こういう条件を満たすものとして、多砲塔戦車が考えられたのは自然の成り行きだったと言えよう。 1930年、ソビエト軍内で、敵戦車を排除しながら、堅固な防衛陣地を突破しうる重戦車を欲した。はじめは、イギリスのビッカース社製作のインディペンデント重戦車の購入を考えた。インディペンデント重戦車は最大装甲29mmと当時にしては重装甲で、32tの車体を398馬力のエンジンで走らせ、最大速度32km/hで走れた。重戦車にしては十分に速い。武装も47mm砲×1、機関銃×5、これ用の砲塔が5つついていた。ようは多砲塔戦車だけども、ソビエト軍の要求する条件にピタリと一致していた。ただし、イギリス側は輸出を許可しなかった。そのため、ソビエト軍は自力で開発を行った。無論参考にしたのはインディペンデント重戦車だった。また、一説にはフランスのシャール2Cも参考にしたといわれている。 1933年始め頃には完成し、T-32と命名された。この型は1933年5月1日のメーデーの軍事パレードに参加している。ただ、T-32重戦車はいわゆる原型車両(プロトタイプ)で、さらに改良が加えられた。改良とは、部品の共通化で、砲塔を快速戦車などと共通化した。こうして1935年に採用されたのがT-35重戦車だった。 T-35重戦車はインディペンデント重戦車と同じく砲塔が5つある。 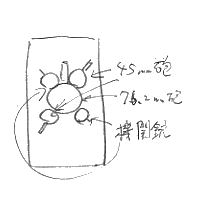 大きな1つは16.5口径75mm砲の砲塔でその周囲、斜め4方向に砲塔が1つずつつけられた。1時半と7時半方向に46口径45mm砲の砲塔が、4時半と10時半の方向に7.62mm機関銃銃塔がつけられた(左図参照)。理屈の上ではどの方向から戦車がきても、歩兵がきても撃退ができた。ただ、真ん中の75mm砲砲塔以外は、互いに射線を邪魔していたので、旋回角度は限られていた。武装はインディペンデント重戦車よりも重武装で、重さも45tに達していた。しかし、エンジンは500馬力の強力なもので、最大速度は29km/hも出せた。これは、重戦車にしては、また、多砲塔戦車にしては速い方だった。しかし、全長が10m近くもあったため、旋回能力は格段に劣った。ちなみに、実戦を経験した戦車で車体全長が9mを越えたのはこの戦車とドイツのマウス超重戦車だけだった(ちなみに、全長世界一はシャール2Cの10.27m)。 大きな1つは16.5口径75mm砲の砲塔でその周囲、斜め4方向に砲塔が1つずつつけられた。1時半と7時半方向に46口径45mm砲の砲塔が、4時半と10時半の方向に7.62mm機関銃銃塔がつけられた(左図参照)。理屈の上ではどの方向から戦車がきても、歩兵がきても撃退ができた。ただ、真ん中の75mm砲砲塔以外は、互いに射線を邪魔していたので、旋回角度は限られていた。武装はインディペンデント重戦車よりも重武装で、重さも45tに達していた。しかし、エンジンは500馬力の強力なもので、最大速度は29km/hも出せた。これは、重戦車にしては、また、多砲塔戦車にしては速い方だった。しかし、全長が10m近くもあったため、旋回能力は格段に劣った。ちなみに、実戦を経験した戦車で車体全長が9mを越えたのはこの戦車とドイツのマウス超重戦車だけだった(ちなみに、全長世界一はシャール2Cの10.27m)。完成時期から、フィンランドとの戦争「冬戦争」に参加したとも考えられるが、実際には分からない。唯一、実戦投入された確実な記録があるのは、独ソ戦初期の頃で、T-35重戦車は国境地帯に配備されていた。そのため、真っ先にドイツ軍と戦火を交えることになったものの、戦火はほとんどなく、ただ、やられる一方だった。理由として、陣地攻撃用だったため、機動性がなかった事、大型のワリに装甲が薄かった事などがある。この2つは致命的な欠点となり、ドイツ戦車の格好の餌食となっていった。ただ、総生産台数も61両とさほど多くはないので、ある程度はソビエト軍も失敗を認めていたとも言えるだろう。たしかに、戦前から多砲塔戦車に見切りをつけて、KV-1重戦車を作ったのだから。ある意味、T-35重戦車は重戦車のアダ花だったとも言えよう。 |
||
一覧に戻る